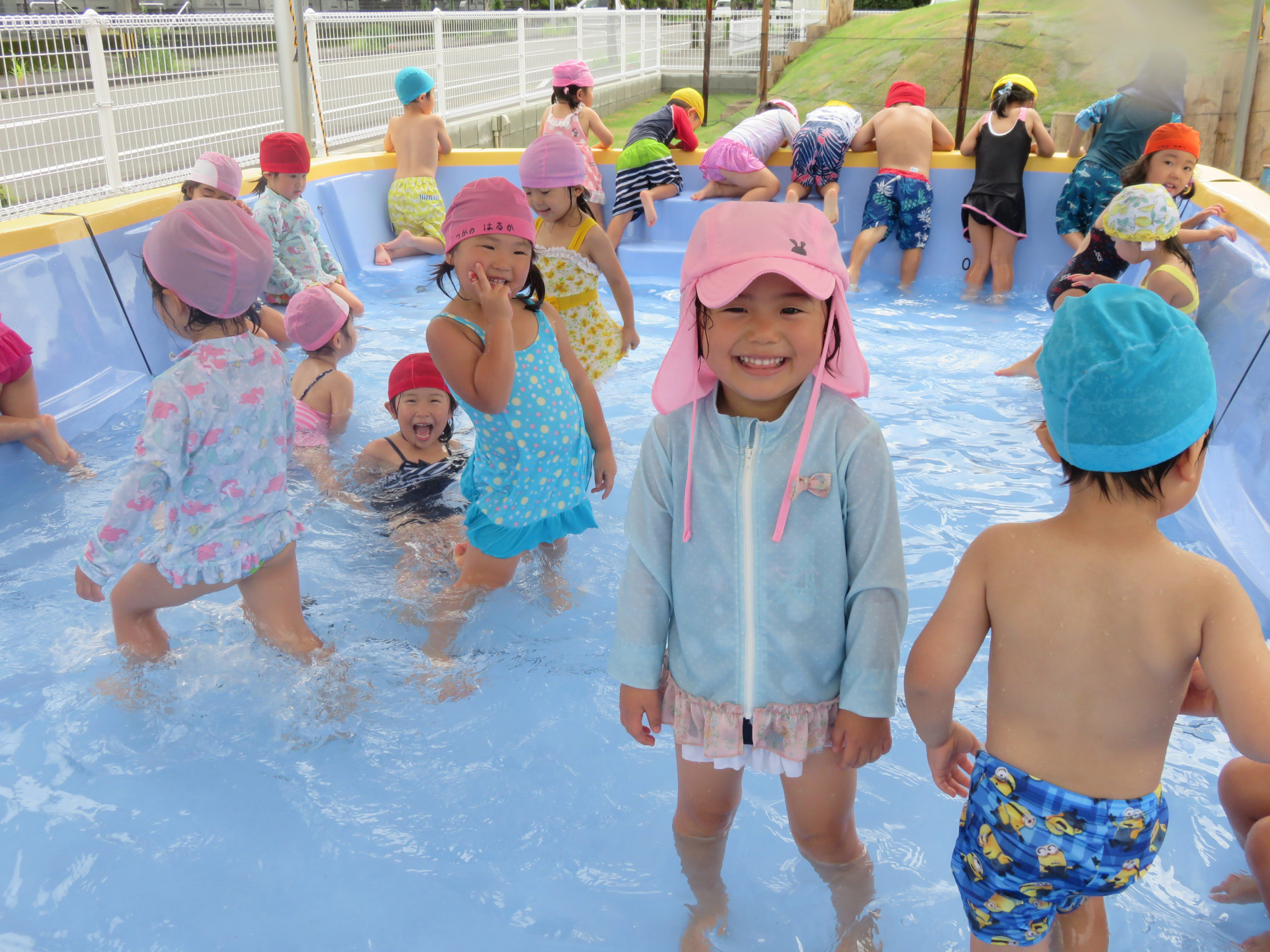
お知らせ
すみれグループさんのお茶教室~令和6年度5月9日
- 2024.05.14
- お知らせ
初夏のすがすがしさが肌に心地よい季節です。
みやこのじょう児童学園では、毎月2回、園長先生によるお茶の教室があります。
お茶の教室を受けるのは、すみれグループ(年長)の園児たちです。
いつもはニコニコと元気いっぱいの子供たちも、お茶教室のときは真剣な表情で、きちんと正座をして園長先生のお話を聞いていました。

すみれグループさんはお茶を先に頂くグループ、お茶を先に点(た)てるグループに分かれました。
みやこのじょう児童学園にある八畳の茶室へ、先にお茶を頂くグループが入室します。
当園のお茶の流派は裏千家です。茶室への入室は右足から行います。

入室して正座で一礼。
右足を立てて立ち上がり、お花と掛け軸の前で再び正座で一礼。
お花と掛け軸へ目線をやり、さらに一礼。

それから自分の席へ向かいます。
練習を始めてまだ一か月。
みんな緊張した面持ちとぎこちない動きでしたが、畳の縁を踏まないよう、綺麗な礼ができるよう、一つ一つの動作を注意深く行っている様子が分かりました。

お茶を頂くグループが茶菓子を頂いた後、正座でじっと待っていたもう一つのグループがお茶を点て始めます。
園長先生のお手本を見つめながら、茶筅(ちゃせん)を上下に細かく動かしてお茶を点てていきます。

細かい泡が綺麗にできると美味しいお茶になりますが、まだまだ練習中のすみれグループさん。
一生懸命、茶筅を動かしますが中々細かい泡ができない子が多くいました。
ですが、中には細かい泡が綺麗にできている子もいました。

お茶が出来上がったら、古帛紗(こぶくさ)の上に茶碗を乗せ、もう一方のグループへ持っていきます。
動かしている足を調整して右足から頑張って入り、正座をします。

「おうすをいっぷくさしあげます」(お薄を一服差し上げます)

そう一言添えて、薄茶を差し出します。
お茶を出した後は退出をしますが、入室のときとは違い、退室は左足からです。
足が多少まごつく子もいましたが、みんなきちんと左足から退室していました。

お茶を差し出されたグループは、左手に茶碗を取り、手前に2回回してお茶を頂きます。
お茶を頂くときは、お茶を用意してくれたお友達に感謝をしていただきます。
一息に飲み切る子もいましたが、ほろ苦い大人の味に苦戦しながら飲んでいる子もいました。

もう一方のグループが再度入室して飲み終えた茶碗を下げると、一度全員退出して、グループを入れ替えて再度これまでの流れを行いました。
茶道は礼に始まり、礼に終わります。
そしてお茶を頂くときは、お茶を頂けることへ、お茶を用意してくれた方へ、感謝の気持ちをもって頂きます。

礼節と感謝の心。
お茶の教室を通して、その2つを養ってほしいと思います。
今年度初めての避難訓練が行われました~令和6年4月30日
- 2024.05.08
- お知らせ
こんにちは。ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
みやこのじょう児童学園では、4月30日に今年度1回目の避難訓練が行われました。
今回の避難訓練は、「火事のときのベルと地震のときのベルを聞こう」「避難のときのお約束を思い出そう」がテーマでした。

みやこのじょう児童学園のホールに、0歳児から6歳児まで、みんなで集まってお話を聞きます。

最初は園長先生のお話を聞いて、「火事のときのベル」と「地震のときのベル」を聞きました。
火事の際の「リリリリリリリリ!」というベルは、みんなビクッとなりながらも、真剣な顔で冷静に聞いていました。
しかし、地震の際の「ゥウ~~~!」というベルはあまりの大きな音に、泣いてしまう子もいました。


火事のときと地震のとき、それぞれの避難方法を園長先生から聞いた後は、避難時のお約束をみんなでおさらいしました。

「お」おさない
「か」かけない
「し」しゃべらない
「も」もどらない
子供たちへ少しでも浸透するよう、先生が一つ一つ「何のお約束だったかな?」と質問します。
それら先生からの問いかけを、みんな大きな声で的確に答えていました。

最後は、園内の各所に置かれている消火器を絶対に触らないように、というお話も聞きました。
とても大切なお話でしたが、長い間みんな集中力を切らすことなく、真剣に聞いていました。
子供たちの日常を壊すような出来事は起きてほしくありませんが、いざというときにこの訓練が小さな命を守ってくれることを願います。




















